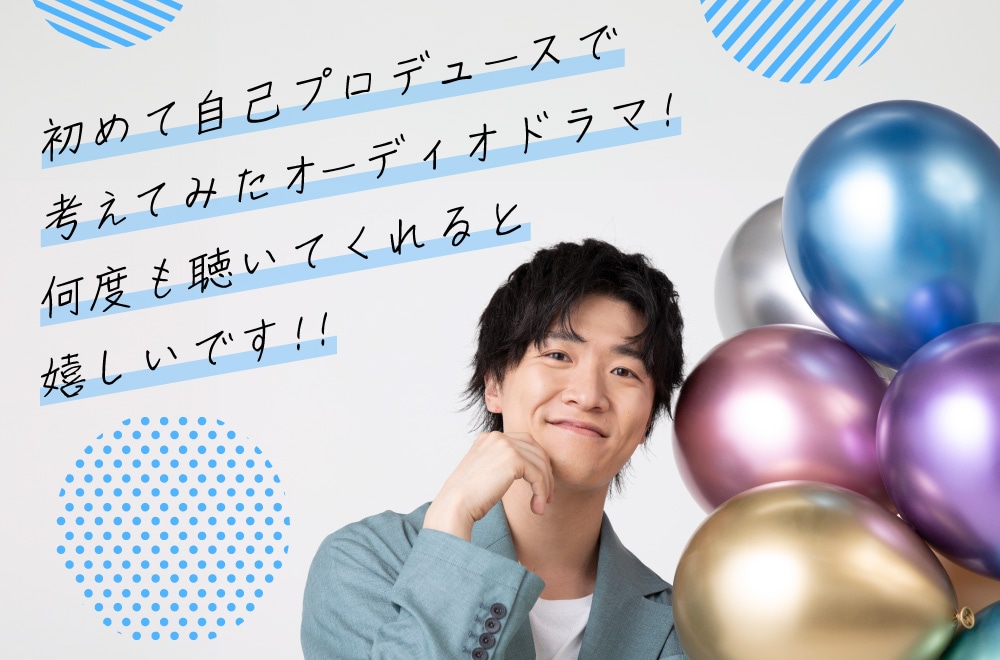思いもよらぬ長丁場だった。
いつものスタッフに囲まれて、メイクを済ませ、ホワイトバックの前に置いた革張りのソファーに座り、冗談のひとつふたつを挟みながら、インタビュアーの質問に答える。
合間にコーヒー。後はスチール写真を何枚か。
と、ここにきて、突然スタジオの電気が消えた。
あっけにとられたような、一瞬の沈黙。
もしやこれは、映画のプロモーション用に仕掛けられたドッキリなんじゃないのか?
しかしすぐにカメラマンの怒声が飛び、辺りをばたばたとスタッフらが走り回る音がする。
マネージャーが携帯のライトで、足元を照らしてくれた。
結局、これは断線による停電で、撮影は一時中断となった。
暗闇の中、待っていても仕方がないので近くの店に移動し、軽食を取った。
『あと、もう少しで直りますから』そんな言葉が何度か繰り返され、結局、スタジオの電気が復旧するまで二時間近くかかった。
それでもなんとか撮影を終え、帰宅したころには時計は深夜を回っていた。
シャワーを済ませ、缶ビールを開ける。と、携帯が震えた。

こんな時間に誰だろう? 画面には友人の名が表示されている。
古い役者仲間だ。
もう10年近く会っていない。
胸騒ぎがして、メッセージを開く。

「(読んで)シアターエイチ、来週取り壊すって……。(ため息)」
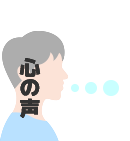
しばしぼんやりとそこに書かれた文字を眺めていた。
返信もせず、携帯を置く。
ビールを一口飲む。
ひどく苦い。
シアターエイチとは、俺がかつて所属していた劇団が所有していた小屋だ。
座席の数は、桟敷を入れても100ちょっと。
色褪せた赤いビロードの緞帳。けぶる煙草と、汗と埃の匂い。

テレビをつけると、お笑い芸人が弾丸トークでひな壇を盛り上げていた。
観客の笑い声がリビングに響く。
あちこちチャンネルを回すと、ケーブル局で珍しく古い映画をやっていた。
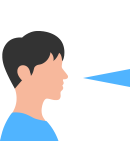
「何だっけなこの映画……」

くすんだ色彩の街並みに、やわらかに差す光の描写が美しい。
主人公の少年が、いたずらっぽく笑った。
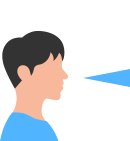
「ああ……」
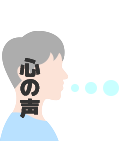
思い出した。新宿の小さな映画館。
あの人と、レイトショーで見た映画だ。

初めて会ったのは19の時。
役者になりたい、ただその思いだけで上京し、ある劇団のオーディションに飛び込んだ。
芝居の経験もない、ただ棒立ちで、与えられたセリフを読んだ。
今思えばひどいもんだ。
だけど、どういう訳かあの人は俺を選んでくれた。
とんとん拍子に役が決まり、順調な滑り出し。
もしかしたら、俺には自分で思っていた以上に才能があるのかも!
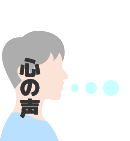
淡い期待は、脆くも初回の稽古で崩れ去った。
セリフどころか、句読点に至るまで、何一つできていない。
共演者たちが稽古を終えて帰っていく中、ひとり、稽古場に残り同じセリフを何度も何度も繰り返した。
稽古場のささくれた床の板目が滲んで見えた。
そんな時、あの人がぽつりと言った。
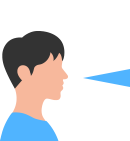
「映画でも、観に行くか」
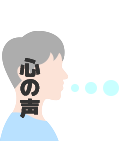
どうしてそんなことを言い出したのかは分からない。
言われるがまま、稽古場を出て、しばらく夜道を歩いた。
たどり着いたのは小さな映画館。
あの人は慣れた様子でチケットを二枚買うと、一枚を俺に放り投げた。
映画は既に始まっていたが、観客はほぼおらず、貸し切り状態だったため中央の席に座った。
俺はあの人の真意がくみ取れないまま、しばらくスクリーンと、あの人の顔をちらちらと交互に眺めていたが……やがて、映画の世界に没頭していった。
映画は素晴らしかった。
恥ずかしながら、それまで数えるほどしか映画を見たことが無かった俺は、終わった後しばらく劇場でぼんやりと作品の世界に浸っていた。
その時、あの人がぽつりと言った。
『いい芝居ってのは、こういうもんだ』
あれから数えきれないくらい、飲んで、叱られ、時にはぶつかり、色んな話をしたけれど。
あの人と並んで映画を見たのは、後にも先にもあれきりだ。
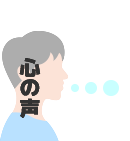
翌日。
午後にぽこっと自由時間が出来たのでシアターエイチに行くことにした。
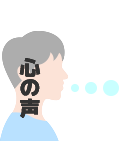
『関係者以外立入禁止』の札が下げられたロープをくぐり、見慣れた入り口のドアを押す。
鍵がかかっている。
当たり前か。
まだ使えるだろうか。
ポケットの中から、古ぼけたキーホルダーの付いた鍵を取り出し、差し込んでみる。
かちり。
乾いた音がして、鍵が開いた。

「(咳)……なんだ、全部そのままじゃないか」

壁に貼られた次回公演のポスター。
作・演出にはあの人の名前。
もぎりの台の横に置かれたパイプ椅子。
ロビーを抜け、ドアから差し込む光を頼りに薄暗い客席へ進む。
床に敷かれた絨毯がところどころ破れ、めくり上がっている。
ステージから客席の端まで、こんなに近かっただろうか。
あの頃は果てしなく遠く見えたものだけれど。
電気はまだ通っているだろうか。
上手側の袖にブレーカーがあったはず……。
と、突然、ベルが鳴り響いた。
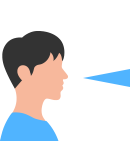
「えっ」

ドアが閉まり、辺りは暗闇に包まれた。
大勢の人の気配がする。
期待と興奮に満ちた、ひそやかなざわめき。
ステージに明かりがともる。
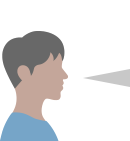
「芝居は終わった。
役者たちはみな空気となり、溶けてしまった。
この幻の建物と同じように、地上にあるあらゆるものはいずれ消え去る。
いま消えていったこの実体のない見世物と同じように」
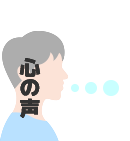
あれは、あそこにいるのは俺だ。
喪服を着て立っている、28の俺。
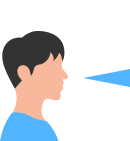
「あ……(引っ張られAD)」

ふいに強く手を引かれ、すぐ脇のシートに座り込んだ。

「あなたは……」
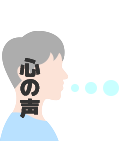
あの人がいた。
隣の席で、俺の手を握ったまま、じっと正面のステージを、舞台の上の俺を見ている。
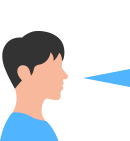
「どうして」
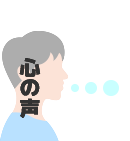
しっ! とあの人が指を立てた。
言われるがまま、俺は同じように舞台を見つめる。
ステージの上では、何人もの俺が、代わる代わるに芝居を続けている。
19、20、23の頃の俺。
若さだけを武器に、跳ねまわっていた頃。
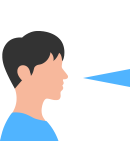
「……ひどいな。もう一度、やり直したい。」

隣であの人がくくっと笑った。
叫ぶように、汗を飛ばして、がむしゃらにセリフを叩きつける俺。
全部覚えている。
あなたと、ここで作り上げてきたもの。
24、25、26。そして……いまの俺。
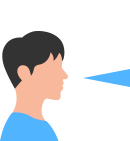
「……嘘だ。あなたは、今の俺を見てないでしょ。」
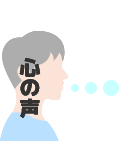
25歳の時。
舞台を見に来た一人のプロデューサ―が声を掛けてくれた。
その後、ドラマで演じた役が当たり、そこから映りの仕事が立て続けに舞い込んだ。
事務所に所属し、これまでとは比べ物にならない額の出演料が入るようになった。
次第に舞台の仕事から遠ざかっていった。だけどそのうちきっと。
ここにはいつでも戻れると思っていた。
忙しさにかまけて芝居仲間とも疎遠になり、あの人とも年に一度か二度、短いメッセージを交わすだけのやりとりを続けること数年。
秋に大きな作品の主役が決まって、案内を送ろうとしていた矢先
――訃報が届いた。
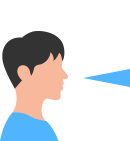
「……もう、見てもらえないんだよ。あなたは、もういないんだから。
弔辞なんか、読みたくなかったよ。
もっと色々教えて欲しかった。
喧嘩したかった。
もっと恩返しがしたかった。
一緒に芝居を作りたかったよ。
なあ!」
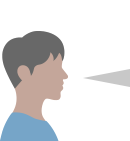
「我々は夢と同じ糸で織られしもの。
この短い人生は、眠りの中を漂う夢に過ぎない。」

俯く俺の横で、あの人がふっと息を吐いた。
満足そうに、笑うように。
俺の手を包んでいたぬくもりが、消えていく。
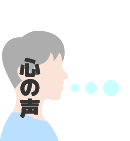
目が覚めた時、俺はリビングのソファーにいた。
テレビ画面からは、映画のテーマソングが流れている。
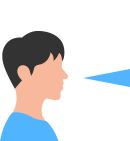
「なんだ……夢か」
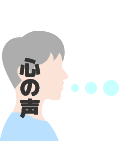
テーブルの上に置かれたままの缶ビールを呷ると、空になった缶を潰した。
あの人が亡くなった後、しばらくしてシアターエイチは人手に渡ったという。
あのままのはずがない。都合の良い夢を見ただけなんだろう。
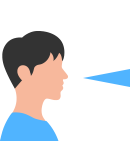
「(ため息)」
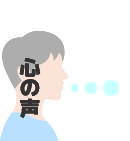
だけど……時々思うんだ。あの時に見たあれが、もしも夢じゃなかったら?
もしもあの世というものがあるのならば、きっとあの人は今でもあの小さな劇場で、あんな風に俺たちの芝居を見てるんじゃないかって。
俺もいつかあそこに行くときは、またあの人と並んで、芝居の話をしたい。
そんなことを思いながら、俺は今日も、台本のページをめくるのだ。